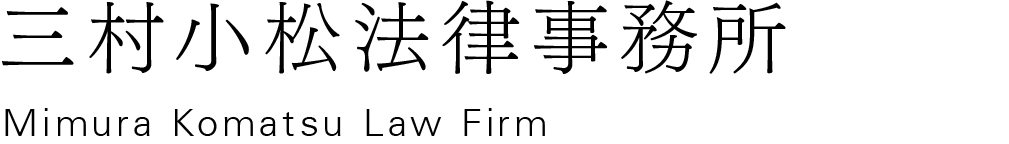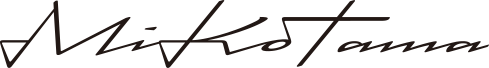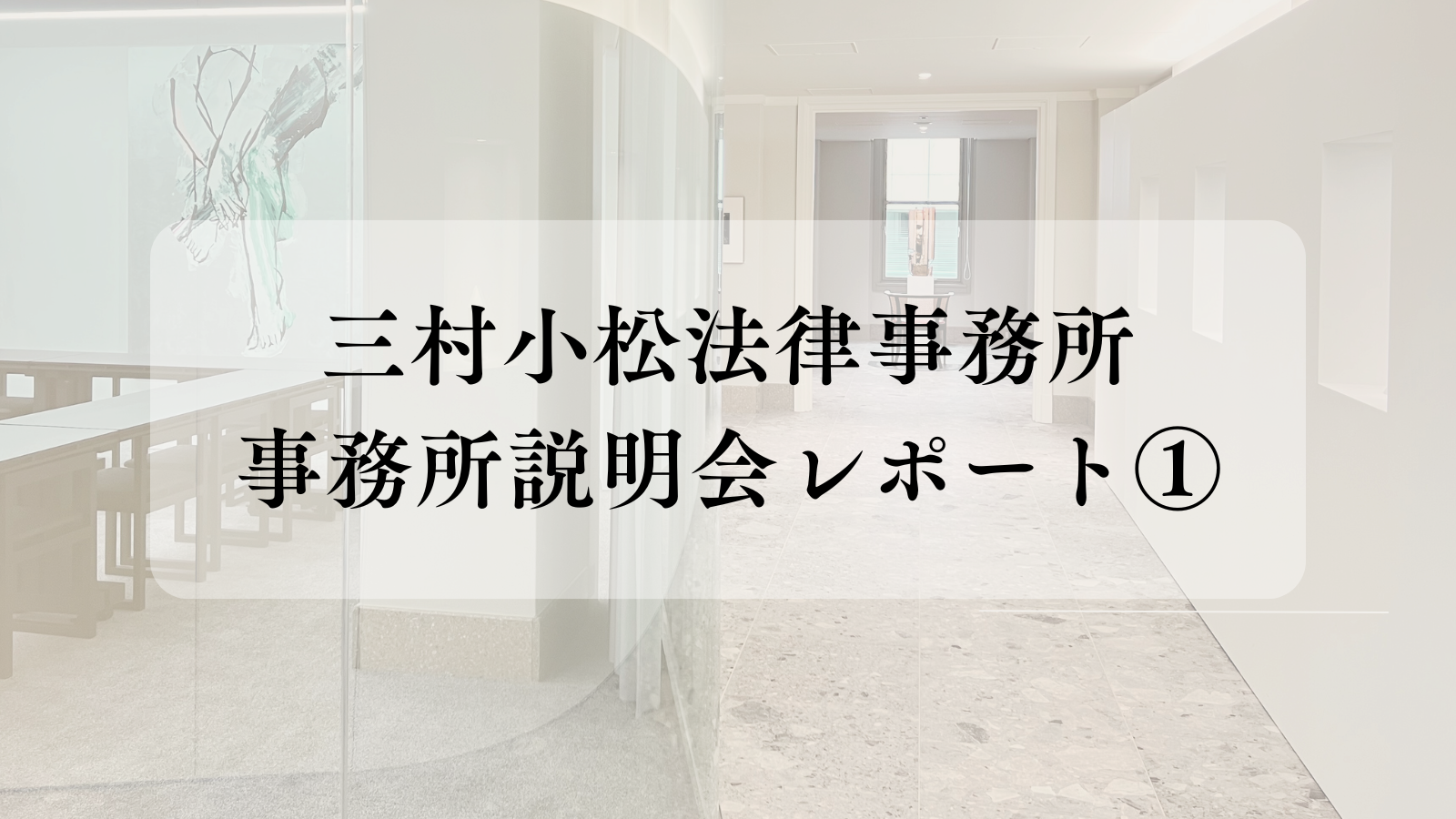アニメや漫画への知見を活かし
キャラクタービジネスに注力
【インタビュー/田邉幸太郎弁護士 前編】
キャラクターコンテンツに造詣が深く、多くの企業やクリエイターをサポートする田邉幸太郎弁護士。現在は内閣府に出向し、行政の立場から、アニメや漫画などが発展しやすい環境づくりに携わっています。
そんな田邉弁護士がキャラクタービジネスに力を入れる理由や業界の課題などについて、全2回でお届けしていきます。
原点は自らを支えてくれた
アニメや漫画への「恩返し」
―三村小松法律事務所では、主にどんな案件を担当されているのでしょうか?
法分野では、知的財産法(特許法、著作権法、商標法、不正競争防止法など)に関する業務がメインです。とはいえ、“知財だけ”という感じではなく、割と幅広く担当しています。
内容的には、様々な契約書の作成・レビューはもちろん、企業間紛争解決やライセンス交渉、クライシス対応などが多いですね。また、労働案件や刑事案件も担当しています。
産業分野では、キャラクタービジネス領域を得意としています。
アニメ―ション・漫画・ゲームなどを制作している企業や、配信サービスやメタバースにおけるサービスを展開している企業のサポートをしたり、アニメーターやイラストレーター、声優、VTuberなど、個人のクリエイターや演者の方からのご相談もお受けしています。
例えば、著名なアニメーターさんや声優さん、TVアニメを作っている制作会社や100万人以上の登録者を有するYouTubeアニメを展開する企業さんなど、おそらく多くの皆さんが目にしたことのある作品を作られている方のお手伝いもさせていただいています。
国外で活躍するイラストレーターさんのご相談や、国内のアニメ作品を国外の配信サービス提供会社にライセンスする契約など、海外が絡む案件もありますね。
最近ではVTuberや生成AIなど、キャラクタービジネス領域に関する講演のご依頼も多くいただいています。また、生成AIについては、特に実演家の「声」に関する問題は力を入れて取り組んでいる領域です。昨年(2024年)の段階でちょっとした論考を書いたり、通称「AILAS」(アイラス)という音声データに関する一般社団法人の活動にも監事として参画していることなどもあり、講演だけではなくメディアの取材依頼なども多くいただいているところです。
―事務所での仕事以外にも、キャラクタービジネスに携わる方向けの無料法律相談サービス「Character-Business and Law」を運営されていますよね。 このサービスを立ち上げたきっかけを教えてください。
個人的にもアニメや漫画、イラストをはじめ、キャラクターコンテンツが好きで、そういった分野の方々のお手伝いをしたいという気持ちがありました。
実際にも業界の方々からさまざまなご相談を受ける中で、「もっと早く相談してくれれば…」「ちゃんと契約してくれていれば…」と感じることが多く、キャラクタービジネス特化で、法的に困っている方々の駆け込み寺を作った方がよいのではと明確に思えたことがきっかけです。
アニメや漫画、イラストが好きな自分だからこそできることもあるのではないかという気持ちからくる勢いもありました。
―イラストやアニメ、漫画が好きだからこそ、キャラクタービジネスに力を入れているのですね。
アニメは幼い頃から自分の傍にずっとあったように思います。休日の朝は「おジャ魔女ドレミ」「プリキュア」「サイボーグクロちゃん」「デジモン」などを楽しみにしていましたし、平日の夕方は「ドラえもん」「クレヨンしんちゃん」「遊戯王」「ベイブレード」「ビーストウォーズ」「メダロット」など、枚挙に暇がありません。
高校生の時に深夜アニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」の3話、ヒロインの一人である長門有希の長回しのシーンを見て、こんな世界観があるのかと頭をガツンと殴られるくらいの衝撃を受けました。そこからは、放送中の作品を追いつつ、過去の深夜アニメ作品のDVDをレンタルショップで借りて見る生活をしていました。もちろん今もアニメ沼にはまったままです。
今キャラクタービジネスに力を入れているのは、より根源的なところでは「恩返し」の気持ちが強いように感じます。
―「恩返し」というのは?
実は、アニメがあったからこそ、今の仕事ができていると思っているんです。
司法試験の勉強をしている時に、ちょっとポッキリ心が折れてしまった時期があって。「今年の司法試験受験はやめようかな」などともやもやして、ずっとアニメ、ゲーム、漫画三昧な日々を送っていました。
そんな時にたまたま、天野こずえ先生の『ARIA The ANIMATION』というアニメを見たんです。作品全体を流れる空気感が本当に優しくて、セリフも素晴らしくてどんどんのめり込んでいきました。
この作品の第3期である『ARIA The ORIGINATION』の中に、昇格試験に何度も落ちてしまい、試験にチャレンジすること自体を躊躇う女性のエピソードがあります。
その女性に対して、主人公が「何時でも何処でも何度でも、チャレンジしたいと思った時が、まっ白なスタートです。自分で自分をおしまいにしない限りきっと本当に遅いことなんてないんです」と声を掛けるんです。
このシーンを見て、今からではもう間に合わないのではないか、また来年で良いのではないかと弱気になっていた自分と重なって、気付いたら涙が流れていて、気持ちがスッと楽になったことを今でも覚えています。
おかげで一気に気持ちの整理ができて、そこからは弱気になることもなく、試験も無事に突破できました。家族や友人の支えに加えて、もう一つ「アニメ」という自分を支えてくれるものが増えて、とても心強かったですね。
自分はアニメに支えてもらったのだから、アニメ業界に何かお返しできることはないかと思ったところ、使えるスキルが法律くらいだったので、自分の知識・経験を使って業界の困っている方のサポートをしようと決めて、今に至ります。

―そんなアニメ、漫画、ゲームが好きな田邉弁護士だからこその強みは、どんな点にあるのでしょうか?
キャラクタービジネスは業界慣習が強く、書籍などに書かれていないこともたくさんあります。
もし弁護士があまり業界に詳しくない場合、業界の方にとっては説明するまでもない事項を最初から説明しなければならず、もうそれだけで時間がかかってしまう。キャラクタービジネスの知見がインプットされている弁護士が対応したほうが明らかに効率的なんですよね。日々キャラクタービジネスに関わっているからこそ、業界の方に寄り添ったサービスを提供できるのではないかと思っています。
また、実際にアニメ、漫画、ゲームなどの作品を愛し、普段から作品に触れているかどうかも、相談内容を理解する上でとても重要だと思っており、その点も自分の強みと感じています。
弁護士へのハードルを下げ
早く気軽に相談できる環境を
―先ほど、「もっと早く相談してくれれば…」と思うことがあるとおっしゃっていましたが、それはどういうことでしょうか?
例えば、何か問題が起こって、すぐに相談をしていただければ、A・B・Cという3つの選択肢を提案できるとします。しかし、「現場の担当者がこう回答してしまった」「既に謝罪してしまっている」など前提条件が増えてから相談いただいたり、対応しないまま時間がたってから相談いただくと、Cの方法しか取れないというケースがあったりします。
また費用面でも、早期の対応ができれば相談料程度で済んでいたものが、紛争化してしまうと費用が高額になってしまうのが一般的です。
このように、早く相談してもらえると、解決策の選択肢や費用の点で大きなメリットがあります。
そこで、まずは早く相談できる場所が必要なのではないかと思ったのです。
―なかなか早く相談できない理由はどこにあるのでしょうか?
“弁護士に相談する”という行為のハードルが不必要に高すぎることは要素として大きいと感じています。「弁護士に相談するのはもっと大規模な紛争のはずで、自分のちょっとした案件で相談なんて…」と思われる方も多いのではないかと思います。
また、一般的に費用が高くなりがちなのは事実です。そういったことが、相談すること自体のハードルを上げていて、結果として、選べたはずの選択肢を自ら手放してしまっているという印象ではあります。
―先ほど業界慣習の話がでましたが、漫画やアニメなどの業界では契約書がないことが多いと聞いたことがあります。
フリーランス法の施行などもありましたし、業界のリーディングカンパニーを筆頭に、しっかりと取決めをしようという機運は高まってきているようには思います。
ですが、残念ながら、取決めを事前にきちんとしておくということが業界全体に定着したとはおよそ言えない状況です。
そもそも、キャラクタービジネスを含むエンタメ業界の特性として、信頼関係や繋がりをとても大事にしているということがあります。契約書がなくても、口頭のやり取りだけで制作は進みますし、多くのケースで特に何も問題が生じていないわけです。そうすると、「契約書を作るなんて言ったら信頼していないみたいだ」、「面倒な奴だと思われて、次から仕事をもらえなくなるのでは」と不安に感じ、契約書を作らないままにしたり、過去に合意した内容が現状に合っていなくてもそのまま使い回さざるを得ないという状況になりやすい。このインタビューをお読みいただいている方の中にも頷いてくださる方も多くいるかと思います。
―冒頭でもご紹介した無料法律相談サービス「Character-Business and Law」では、具体的にどういった相談が多いのでしょうか?
多いのは、ビジネスについてちょっと相談したい、意見が聞きたいといった感じのご相談ですね。例えば、「グッズ販売は事業でやっているけれど、新しくIP開発をすることになったが、どういうところに気をつけたらいいか」「このビジネススキームにはどういう法的リスクがありそうか」といったご相談です。
ビジネスの早い段階からどういったことが問題になりそうかを把握しておくことは重要ですから、とてもよい使い方をしてくださっているなと感じます
ークリエイターさんからはどんなご相談がくるのでしょうか?
「イラストを描いたんだけれど、他の方のイラストと似ていると判断されるか」、「Xでこういうリプライが飛んできているが、相手に連絡をして弁明をした方がいいのか」、「こういう状況なんだけれど、提出した成果物について、私はどのような権利を主張できるのか」など本当に様々な相談があります
また企業・個人に関わらず、最近は生成AIに関するご相談も増えていますね。
「Character-Business and Law」が小さなきっかけとなり、キャラクタービジネスに関わる方々が弁護士に相談しやすい環境が広がるといいなと願っています。
後編では、現在出向中の内閣府での活動や、生成AI、声の権利に関する取り組みなどについて詳しく聞いていきます。
お楽しみに!
【2025.3.7】
法律相談・メディア出演のご相談はこちら
お問い合わせMiKoTamaメルマガ
法律に関する様々な情報トピックをメルマガで配信