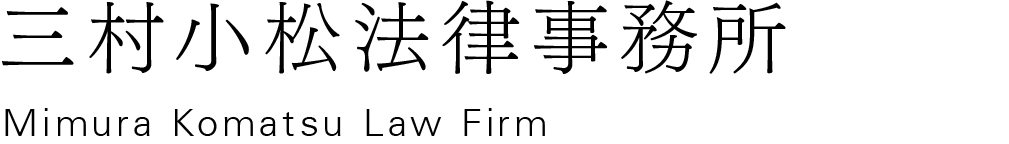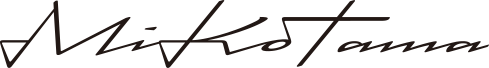得意分野
弁護士 / 東京大学教授
Attorney / Professor at the University of Tokyo
玉井 克哉
TAMAI Katsuya

TEL:03-5218-5260
FAX:03-5218-5263
tamai【at】ip.rcast.u-tokyo.ac.jp
※上記の【at】を@に置き換えて下さい
第一東京弁護士会
Dai-ichi Tokyo Bar Association
FAX:03-5218-5263
tamai【at】ip.rcast.u-tokyo.ac.jp
※上記の【at】を@に置き換えて下さい
第一東京弁護士会
Dai-ichi Tokyo Bar Association
得意分野
学歴・職歴
- 1983年 東京大学法学部卒業
- 1983-86年 東京大学法学部助手
- 1986-88年 学習院大学法学部専任講師
- 1988-90年 学習院大学法学部助教授
- 1989-92年 マックス・プランク知的財産法研究所客員研究員
- 1990-96年 東京大学法学部助教授
- 1995-97年 東京大学先端科学技術研究センター助教授
- 1997年-2024年 東京大学先端科学技術研究センター教授
- 1999-2000年 ジョージワシントン大学客員研究員
- 1999-2000年 連邦巡回区合衆国控訴裁判所客員研究員
- 2008-13年 慶應義塾大学特別招聘教授
- 2016年-24年 信州大学経法学部教授
- 2019年- 三村小松法律事務所
- 2025年- 東京大学先端科学技術研究センター特任教授
- 2025年- 信州大学経法学部特任教授
著書・論文
- 「米国特許法における2種類の判例 ―連邦巡回区控訴裁判所と合衆国最高裁判所」『切り拓く ― 知財法の未来 三村量一先生古稀記念論集』 (共編著)日本評論社
- 「特許法上の査証手続とその遠隔方式での実施について ―強制色の乏しい仕組みによる制度間競争の成否」『NBL』1268(2024.6.15)号 商事法務
- 「米国経済スパイ法・再訪 ~主権国家による産業スパイ事件をめぐって~」『信州大学経法論集』信州大学経法学部
- 『経済安全保障の深層 課題克服の12の論点』(共編著) 日本経済新聞出版
- 「特許出願非公開制度 : 機微技術の流出防止のための有効な手段となるか」『年報知的財産法2022-2023』(共編著)日本評論社
- 「裁判所における「熟議」―グーグル対オラクル著作権侵害事件におけるアミカス・ ブリーフを素材に―」『Nextcom』2020 巻, 42 号 株式会社 KDDI総合研究所
- 「商品識別番号の改変と商標権侵害 : 商標の品質保証機能を重視する立場から」『知財管理』2020年5月号 日本知的財産協会会誌広報委員会 編
- 「米国の秘密特許制度について」『A.I.P.P.I.』 63巻11号 日本国際知的財産保護協会
- 『園部逸夫 オーラル・ヒストリー: タテ社会をヨコに生きて』(共著)法律文化社
- 他多数