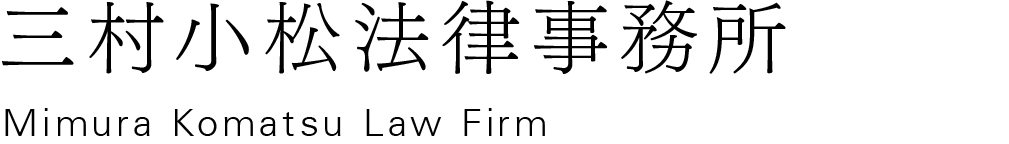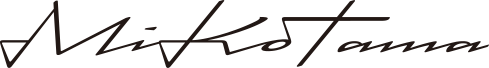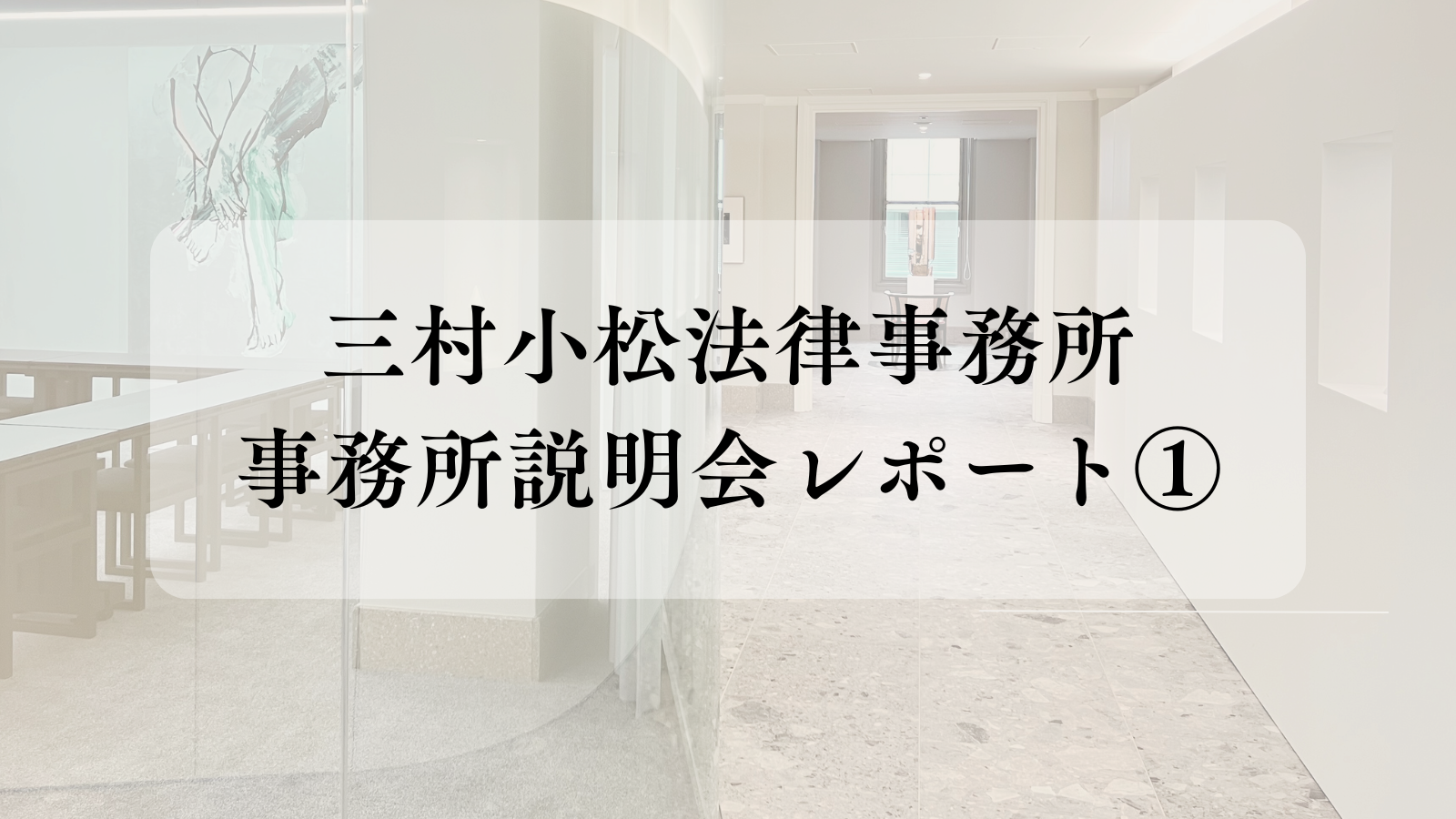事業創造に寄り添う法務の可能性と
エンタメの現場から学んだ無争の哲学
【インタビュー/杉本直樹弁護士 前編】
この秋、三村小松法律事務所に移籍した杉本直樹弁護士。これまで著名な芸能プロダクションに出向し役員直轄の事業調整部門に所属、法務の知見を活かしながら現場スタッフとの橋渡し役を務めてきました。
さらには映画やテレビ番組のプロデューサー業務にも携わるなどエンターテインメント分野で培った経験は弁護士として異色の経歴といえます。
訴訟にとどまらず、依頼者とともに最適解を模索し、前向きな事業を創り上げる姿勢を大切にする―。弁護士という職へかける思いや哲学、そして実務に至るまでお話をうかがいました。
法務の枠にとどまらず
事業創造のパートナーとして伴走
―まず、弁護士を目指された理由を教えていただけますか?
幼い頃から正義の味方への憧れが人一倍強く、戦隊シリーズや刑事ドラマに夢中になるテレビっ子でした。木村拓哉さん主演のドラマ「HERO」も好きで、大学を卒業するころまでは検察官を志望していたんです。ただ、実際の仕事内容を知るうちに、自分が目指す職業としては弁護士の方が向いていることがわかってきて方向転換しました。 同時にテレビなどエンターテインメントを通じて人を笑顔にできるようなコンテンツも作ってみたい、という志望も持ち続けていました。
自分の好奇心も大切にしながら一生ワクワクし、新鮮味のある仕事をしたい、でもストレートにテレビ業界へ入ってキャリアを積むよりは、ある種の専門性を持って関わった方がより面白く、新しい価値を生み出すことができて業界の発展へも寄与していけるんじゃないか? と考え、弁護士になりました。
―一般的に弁護士というと硬い職業で、クリエイティブとは真逆の印象もあります。
確かにそういうイメージも強いと思いますが、私は弁護士の役割はもっと多様であっていいと考えています。 弁護士は民間の職業でありながら公益性も帯び、その責任感や信頼性は社会から一定の評価を受けています。それを企業の方に“無形資産”として捉え、活用していただくことで、トラブル対応にとどまらず、事業創造のパートナーとして伴走できるのではないか、と考えています。 コンサルティング的な側面を持ちつつも、法務という確かな裏付けを備えた支援を提供できるのが弁護士の強みだと思うのです。
一般的に弁護士がエンタメ企業に関わる場合、契約書や法務対応を任されることが多いですが、私の場合はややイレギュラーで、顧問弁護士や会計士の方とは別に、現場との橋渡し役を担うことが少なくありません。たとえば会議に同席し、現場スタッフに代わって専門家に質問したり、課題を整理して一緒に解決策を探ったりする。そんな役割を果たしてきました。
―弁護士の枠を超え、これまで映画のプロデューサー的な役割も担われてきたそうですね。
もちろん本職のプロデューサーの方々のように全てを担うわけではありませんが、彼らと並走しながら、これまで業界であまり語られてこなかった課題を問題提起したり、意見交換をしたりしてきました。作品ごとに最適解は異なりますが、数々の現場で見聞きした臨場感や実態を踏まえると、「ここからなら変えられるかもしれない」というポイントが見えてきます。そうした視点を共有できる仲間とともに、模索しながら進めていく、その過程こそが自分にとって大切な経験になっています。
―事例としては労働基準法に関係したものが多いでしょうか?
そうですね。エンタメの現場では、どうしても労働基準法を完全に遵守するのが難しいケースが出てくることがあります。ただ「違反になるから守る」という発想にとどまらず、なぜ守る必要があるのか、守った先にどんな価値があるのか? その目標を現場全体で共有し、前向きな気持ちで作品づくりに取り組めることが理想だと考えています。 また、雇用関係や上下関係に起因するさまざまなハラスメントの問題も、クリエイティブの現場では大きな課題です。立場の違いにかかわらず忌憚のない意見を言える環境、つまり精神的な安定性を備えた職場環境を作れたらいいな、とは常々考えていることです。
最近では映画制作の現場で性的なシーンを撮影する際にインティマシー・コーディネーターが参加するケースが増えています。私はそれをさらに拡張し、演者だけでなくスタッフ全体を対象にした心理的安全性=サイコロジカル・セーフティ(Psychological Safety)を確保するためのコーディネーター(P Sコーディネーター)がいてもよいのではないかと考えています。
―現状、そういう役割の方は現場にはいらっしゃるのでしょうか?
いないんです。だからこそ、現場で起こりうる課題について意識共有するためにも、PSコーディネーターを通じてオープンに話し合える環境があれば、支配的な関係性が固定化されるリスクを減らすことができ、作品づくりにとってもより良い環境になると思います。 例えばP Sコーディネーターを採択したプロデューサーには、国や映画関連団体から補助金が出るとか、そういった仕組みを作れば、制作に関わる人たち全員が働きやすく、クリエイティブに集中できる環境が生まれ、結果、より質の高い作品が生まれていく。そんな前向きな流れができていったらいいですよね。
―その流れは映画などエンタメの業界に限らず、どの業界のどの職場でも汎用性がありそうです。
そう思います。職場環境の整備がもっとも難しいと言われるエンタメの現場で実例が生まれれば、「他の業界でもできないのはおかしいよね」という問題提起にもなります。まずはエンタメの現場から少しずつでも変革していけたらいいな、と思っています。
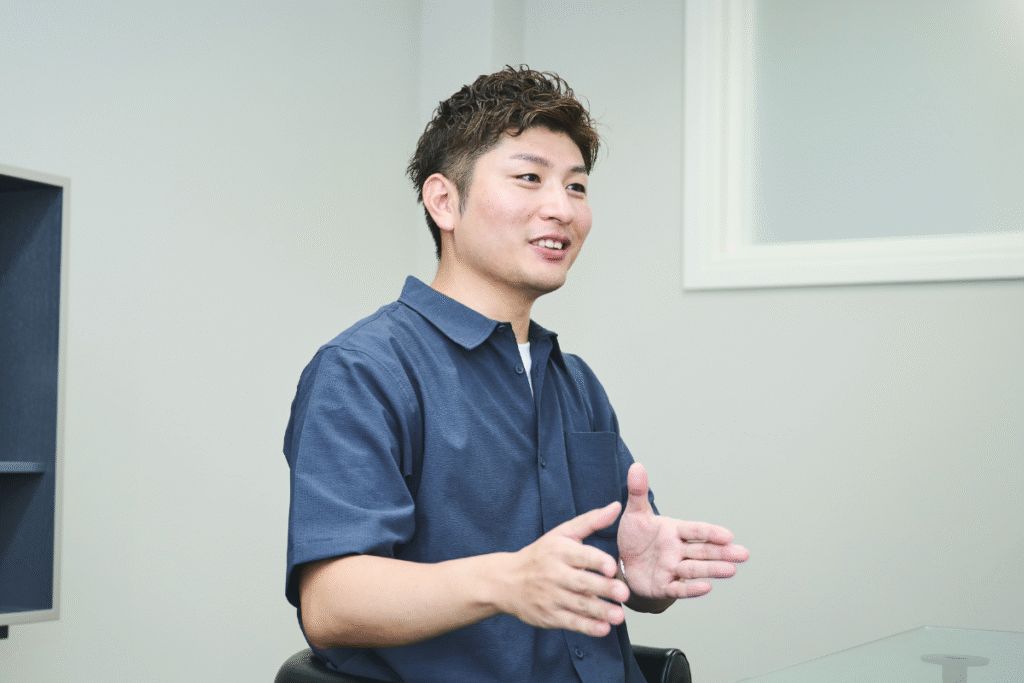
不毛な争いをなくすため
訴訟の先にある本質を見据えて
―昨今、芸能界やテレビ業界ではハラスメント問題が大きくクローズアップされています。 社内にコンプライアンス室を設けたり、また調査の一環として第三者委員会が設置されたりする動きもありますが、この一連の流れについてはどうご覧になっていますか?
コンプライアンス委員会や第三者委員会は、基本的には「問題ありき」で改善提案を行うところまでで、あとは現場に委ねられることが多いですよね。弁護士や専門家が関わる場合、そこまでが職業上の限界でもあります。しかし、専門家としての背景を持ちながらも、最終的な正解を出すのではなく、あくまでアイディアとして提案を示し、現場の人と一緒に考え、掛け算をしていくように何かを生み出していく余地もあるのではないか? と考えています。
問題解決に際して弁護士がお墨付きを与えるという立場ではなく、法律の専門知識を背景にしつつ一個の人間として問題に対峙し、自分の考えとして提案する。その上で現場の人たちがどのようにそのアイディアを有効活用していくかを考える、という流れができれば、もっとポジティブかつ建設的な形で弁護士が問題解決に関わることができると思います。
―弁護士としてはそういったスタンスでクライアントさんと関わるのは珍しいのではないですか?
実を言うと、私自身が争いごとを苦手としているので、「いかに不毛な争いを無くしていくのか」ということを常に考えています。確かに、訴訟に関わるのが弁護士の仕事ですので、争いを無くしていくのは職制上の矛盾でもあります。しかし、私にとって“無争”を追求することは、終わることのない人生のテーマのようなものとしてずっと考え続けています。争う前に、その先に何があるのかを含めて目の前のトラブルに向き合ってほしいといつも願っています。
弁護士としての役割は争いを解決すること――これは変わらない事実であり否定しません。ただ、私は“争い”と“闘い”は本質的に異なると考えています。争いとは「自分の利益を最大化することを目的とする、テイカー同士の利益獲得行為」である一方、闘いとは「当事者が本来保護されるべき権利、および法が想定する利益を実現する行為」だと考えます。 “闘い”に勝つためであれば、裁判や訴訟はどんどん活用すべきだと思いますが、日常的に多くの方が直面する“争い”は、本質が見えにくくなっていることも少なくありません。実際に発生している訴訟の場面では登場人物間のコミュニケーションエラーなどに起因し、自己の利益を最大化することを目的とした“争い”であることも少なくないと感じています。
例えば訴訟に勝って賠償金を獲得しても、果たしてその結果に満足できるのか? お金を介した和解で全てがすっきり解決するわけではありません。和解として表面的には丸く収まったように見えるかもしれませんが、当事者の感情や関係性までは完全に整理されないことも多いのです。
―確かにお金を払う側や訴訟に負けた側に立てば、スッキリしないですよね。
そうなんです。そもそも争っている時間自体がもったいない。人生は限られていますから、色々な楽しいこと、やりたいこと、人との出会いによって広がっていく可能性がたくさんあると思うので、究極の理想は全員が1分1秒でも長く前向きなことに関われる、クリエイティブな時間で満たされて欲しい。 少なくとも自分が出会った人たちは、そんなアプローチで豊かな人生を送っていただきたいので、弁護士としての仕事を通じ、そうした土壌を作る取り組みを続けていきたいと考えています。
<後編>では三村小松事務所に移籍した理由やエンタメ現場での具体的なトラブルについてお話しいただきます。
【2025.10.1】
三村小松法律事務所では、当事務所の理念や目標に共感し、チャレンジ精神をもって行動できる方、また各業界への関心やこれまでの経験を活かして成長したいと考える意欲ある弁護士を募集しています。
採用ページ
法律相談・メディア出演のご相談はこちら
お問い合わせMiKoTamaメルマガ
法律に関する様々な情報トピックをメルマガで配信