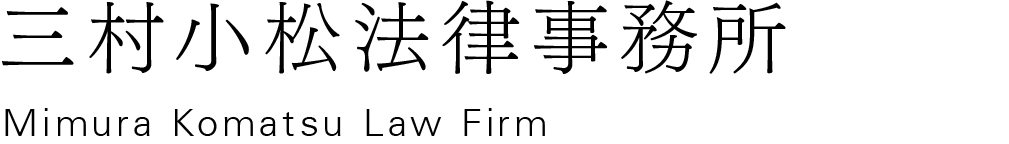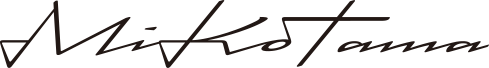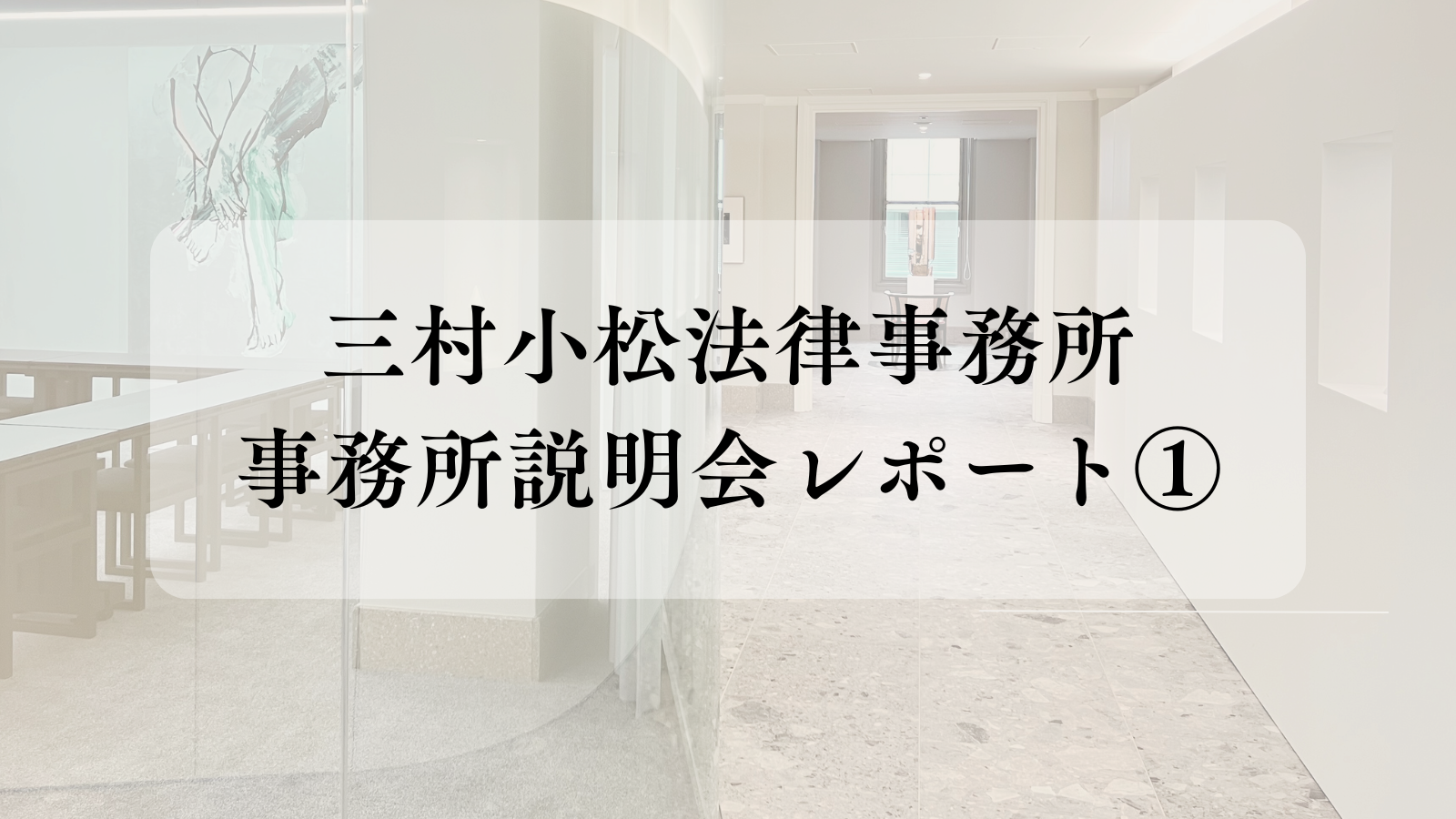事業創造に寄り添う法務の可能性と
エンタメの現場から学んだ無争の哲学
【インタビュー/杉本直樹弁護士 後編】
この秋、三村小松法律事務所に移籍した杉本直樹弁護士。これまで著名な芸能プロダクションに出向し役員直轄の事業調整部門に所属、法務の知見を活かしながら現場スタッフとの橋渡し役を務めてきました。
インタビュー後半では、三村小松法律事務所に移籍した理由や、エンタメ現場での具体的なトラブル、契約交渉やコミュニケーションの工夫などについてお話をうかがいました。
<前編>はこちら
感情に寄り添い
対話から解決を導く
―三村小松法律事務所に移籍された理由について教えていただけますか?
今後もエンタメ関連の案件を中心に携わる予定ですが、実はこの分野の判例や事例はまだ多くありません。というのも現場の課題はなかなか表に出てこないことが多く、契約や著作権法など参考にできるルールはあるにはあるんですが、そこだけで解決できない問題も少なくありません。また、解釈を自分一人で行うと、どうしても価値判断に偏りが出るリスクもあります。
弁護士業界ではレアなことですが、三村小松法律事務所は業務をチーム体制で行うことも多いので、自分とは異なる発想を持った弁護士の人たちと意見交換することで、より回答を洗練させることができたり、もう一歩提案を発展させたりすることが可能になってきます。
また、争いをできるだけなくしていきたい、という自分のテーマからするとパラドックス的でもあるのですが、三村小松法律事務所は訴訟に強いということも魅力でしたね。元裁判官の弁護士が4人在籍しており、訴訟の実例や経験値を多く持っているからこそ、案件として意義深い訴訟なのか、もしくは回避すべき紛争なのかを説得力を持って判断できます。
さらに、代表の三村弁護士をはじめ知的財産分野にも強みを持つため、エンタメにとどまらず、さまざまな業界のビジネスをどう発展させていくか、という事務所としての深い知見も学びながら実務に活かせる点も大きな魅力だと感じています。
―最近は日本映画界でも次々と話題作が生まれ、海外からの注目も高まっているようです。現在も映画のプロデュースは手がけていらっしゃるのですか。
はい、ちょうど原作の許諾がとれた作品があって、開発に動き始めたところです。
大手の映画会社であれば製作委員会を組織し、全体を俯瞰できるスタッフが揃っていますが、小規模な場合は現場の感覚で契約書すら存在しないケースも少なくありません。そのため、私は管理面を担う人員として現場に参加することがあります。肩書としてはプロデューサーのひとり、となるのかリーガルプロデューサーなのか定かではありませんが、目標は来年撮影して、再来年に公開、というスケジュールでいけたらいいなと思っています。
もっとも映画というのは構造的に大きな収益を見込みにくく、むしろ赤字になることが結構多いんです。それでもなお新作が発表され続けているのは、本来の産業構造からするとすごく特殊な業界だと思います。
―それはなぜだと思われますか?
映画ってやっぱり理屈じゃなくてロマンを追い求めている人たちが昔からずっと存在しているんですよね。だからどんなに予算が限られていても映画は作り続けられるし、決してなくならない。
たとえ映画館で上映するというスタンスが変わっても、映画という表現コンテンツ自体は必ず残っていくと思います。
―映画などエンタメ系の現場ではやはり契約書なしに物事が進んでいくことが多いものなのでしょうか。
本来は書面を作るのが理想ですが、現場の事情や関係者の思惑もあって残せないとなった場合どうするか。その際は「ここだけは最低限押さえておきたい」というポイントをメールで送っておき、相手から明確な言質をとっておく、というアドバイスをすることもあります。のちにコミュニケーションエラーが起きないように、重要な部分だけでも文書として残し、双方の認識に齟齬がないようにする、というエビデンス・マネジメントですね。
また、相手が意図的に曖昧にしている可能性がある場合には、ロジカルに指摘しつつも、追及しすぎて対立を招かないようバランスを取ることも大切です。正論を振りかざして衝突するのではなく、相手が「ノー」とは言えない形で、必要な確認をきちんと積み重ねていく。そのための文言を一緒に考えることもあります。
―つまり、すべての事項を網羅した完璧な契約書をつくることだけが正解ではない、ということですね。
そうですね。契約交渉の過程で、最終的な文言としては採用されなくても、「この点についてはこういう解釈で合意していましたよね」と経緯を残しておくことも重要なコミュニケーションになると思います。契約書は本来、将来的な齟齬を防ぐためのものですが、何かトラブルが生じた際に文脈が読み取れなければ、そこから争いに発展しかねません。だからこそ、締結までの流れを必要に応じて適切に可視化しておくことも大切なんです。
また、ある意味ではクリエイティビティに直結しているのかもしれませんが、自分のイズムや信念が強い人ほどトラブルに巻き込まれやすいとも感じています。常に自分が正しいと思い込みやすく、他者の価値観の違いを認められないと、相手を排斥したり攻撃したりして衝突につながってしまう。その積み重ねが、結果的に作品やイベント自体に負の影響を及ぼしてしまうのです。
エンターテインメントは本来、夢をクリエイトしていくものですから、作り手自身が疲弊せず、前向きな気持ちで取り組める環境を整えることが創作意欲を支え、作品の面白さにも直結すると思います。
現場では時に、大きな声を張り上げて威圧することで緊張感をつくろうとする人もいますが、それは時代錯誤かな、と思います。より洗練されたアプローチで健全な緊張感のある環境をつくることこそ、プロデューサーや監督、スタッフを統率する立場の人間に求められているのではないでしょうか。
そういう意味では、強いイズムを持つ方々に柔軟性を促し、対話を通じてよりよい方向へ導いていくのが、私自身の役割だと感じています。
―法律だけで仕切れるものでもなく、メンタルに訴えかける必要があるのでなかなか難しそうな役割ですよね。
中には、事の発端となった言動をした人が自分でも無茶苦茶なことを言っている自覚がありながら、振り上げた拳をおろせないでいる、というようなケースもあり、その場合は「そのおろし方を一緒に考えましょうか?」といったスタンスで一緒に向き合います。「拳を上げた」主体が相談者であることもあれば、相手方のこともありますが、相手方の場合は無闇に論破したり、追い込みすぎたりするのではなく、相手が「拳をおろしやすいシナリオ」を考えることも重要な視点だと思っています。
また、法律的に見れば、通すのは難しいと判断せざるを得ないご相談であっても、その背景にある不満や相手方とのコミュニケーションを丁寧に紐解いていくと、当事者の方が冷静さを取り戻し、結局のところ「何が幸せなのか?」を改めて考えるきっかけとなることもあります。
もちろん私からは法律的な論点もお伝えしますが、結局解決には法律を全く使ってなかったな、という笑い話のようなこともありますね。
―相談者の方も、話を聞いてもらうこと自体で落ち着きを取り戻し、自ら納得されるに至ったのかもしれませんね。ある意味、セラピー的なセッションのような。弁護士として表面的な対応にとどまらず、想像力や思いやりを持って対処されているのかな、と感じます。
たとえ解決できなかったとしても「会って話をしてよかったな」と思って帰っていただけたら、という気持ちと姿勢は大切にしています。“争いが嫌いな弁護士” として争いを根本的に減らすための取り組みは、法律論だけでは片付かないものも多くありますから。
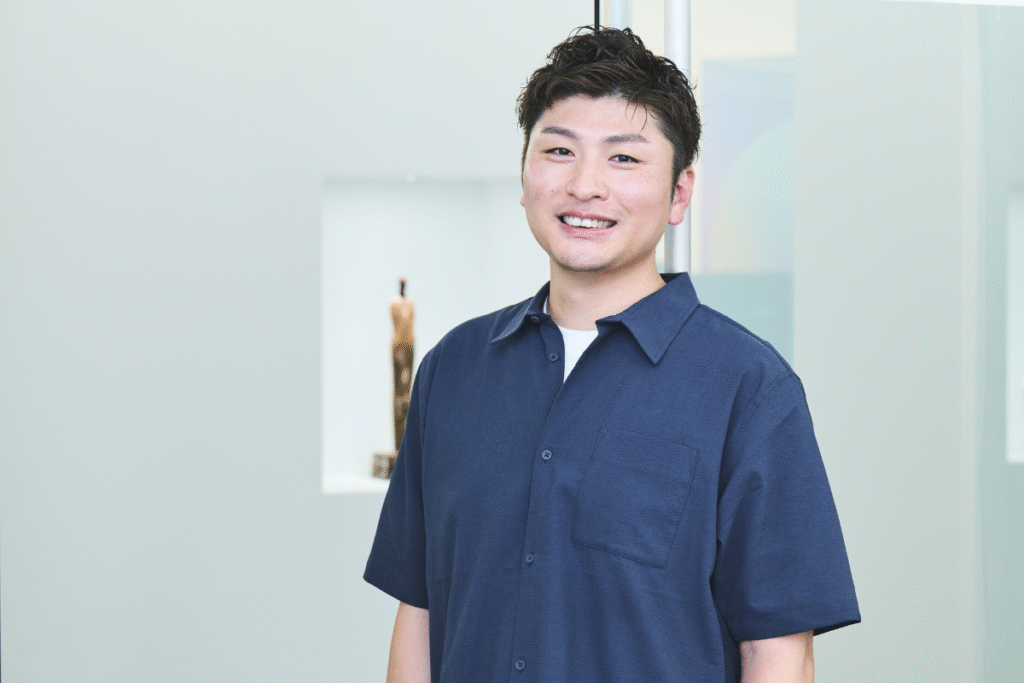
【2025.10.3】
三村小松法律事務所では、当事務所の理念や目標に共感し、チャレンジ精神をもって行動できる方、また各業界への関心やこれまでの経験を活かして成長したいと考える意欲ある弁護士を募集しています。
採用ページ
法律相談・メディア出演のご相談はこちら
お問い合わせMiKoTamaメルマガ
法律に関する様々な情報トピックをメルマガで配信