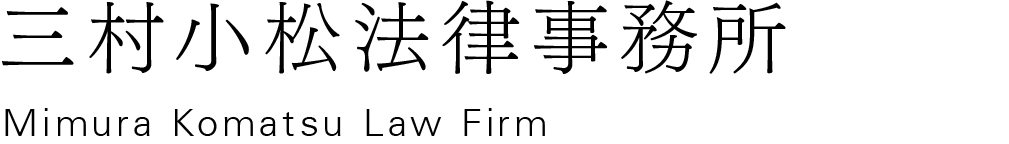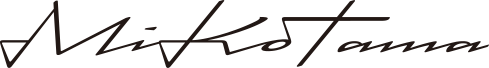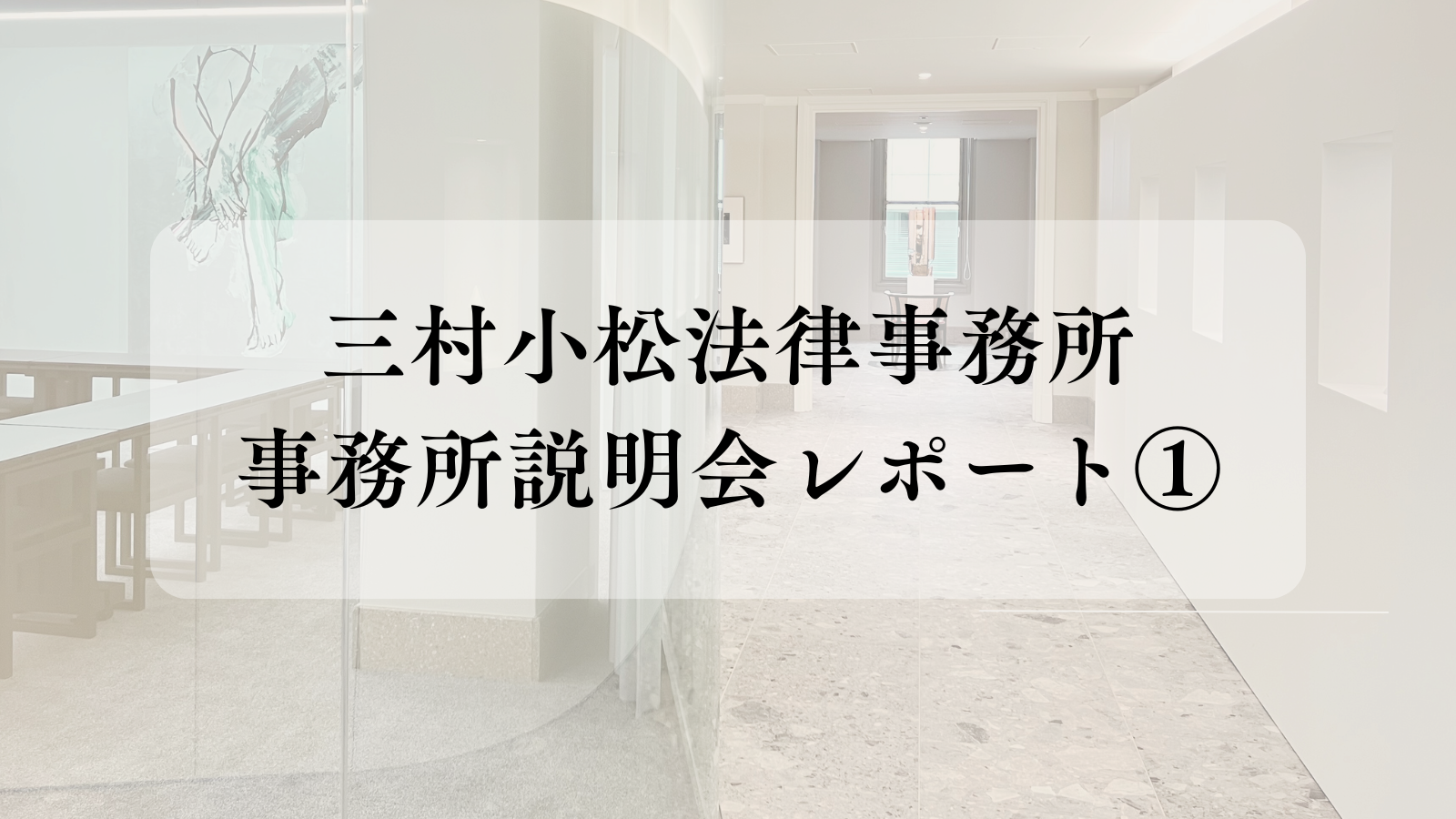探求心を原動力に
訴訟弁護士が歩む宝飾の道
【インタビュー/新田真之介弁護士 】
「ジュエリーロー」を得意とする数少ない弁護士、新田真之介弁護士。2025年1月に三村小松法律事務所に移籍し、クリエイティブ分野に強みを持つ当事務所のサポート体制はさらに強固なものになりました。
新田弁護士は移籍前から当事務所の海老澤弁護士や小松弁護士が、「ファッションロー」や「アートロー」といった新しい産業分野に挑戦し、法律の枠にとどまらず幅広いアドバイスをされている姿に強く共感していたそう。
NoteやPodcastなどでも積極的に発信を行い、ジュエリー業界の可能性と業界ならではの課題に向き合いながら独自のキャリアを築く新田弁護士に、これまでの歩みと見据える未来をお聞きしました。
論理性と経験を培う中で
虜になったジュエリーの魅力
―学生時代はディベート部に所属されていたそうですね。
中学まではサッカー部に所属していましたが、授業でディベートを体験したことをきっかけに論理を組み立てて議論する面白さに惹かれ、高校ではディベート部に入部しました。
活動は想像以上に本格的で、「ディベート甲子園」と呼ばれる全国大会にも出場しました。論題が年度初めに発表され、夏の大会に向け、チームで数か月かけて徹底的に準備を進めるのですが、試合ごとに肯定側・否定側の立場が変わるため、どちらの立場からでも戦えるように準備を整える必要がありました。
立場を切り替えて論理を組み立てる作業は大変でしたが、その過程で多角的に考える力や入念に準備する姿勢が培われていったと思います。
そして何より勝敗がはっきり決まるというゲーム性に夢中になりました。負けず嫌いな自分にはぴったりの競技だったと思います。
―学生時代からすでに論理的に考える力が培われていたのですね。
子どものころから弁護士を目指していたのですか。
いいえ、実は高校3年までは理系を選択していて、将来は研究職に進むことも考えていました。ただ、当時は裁判員裁判制度の導入をめぐる議論が社会で盛んに行われていて、福岡県弁護士会のシンポジウムに参加した際に「法律が社会全体に直結している」ということを実感した経験から法律に興味を持ち、法学部も併願してみたところ、合格して本格的に法律に触れるようになったんです。
法学部入学後も、はじめは理系の知識を生かして弁理士になろうかなと考えていましたが、学びを深めるうちに司法試験への関心が高まり、最終的には弁護士を志すようになりました。
司法試験の勉強は苦しい時期が多かったですが、ディベートで培った論理的思考や文章力が役立ったと思います。仲間と議論し合いながら、部活の延長のような感覚で取り組めた部分もありました。
これまで好きでやってきたことが、そのまま試験を乗り越える力になったのは幸運だったと思いますね。
―弁護士になってからはどのような分野のお仕事をされたのですか
主に中小企業の経営支援や損害保険に関する案件に携わってきました。
中小企業の経営支援の分野では、経営者の方から「長年信頼していた社員による裏切り」のようなご相談をいただくことも多く、金銭的な損失だけでなく心理的なダメージも大きいため、法的対応にとどまらず再発防止を含めた仕組みづくりを意識してきました。
損害保険の分野では、不正請求に関わる事案を数多く経験してきました。典型的なものは、共謀して事故や盗難を装う請求、あるいは同一商品の重複請求といったケースです。一見すると巧妙に見えても、本人の申告内容とさまざまな証拠を照らし合わせていくと、徐々に実態が見えてくる。そうした経験を通じて、「事実をどう見極めるか」という視点が自然と養われていったように思います。
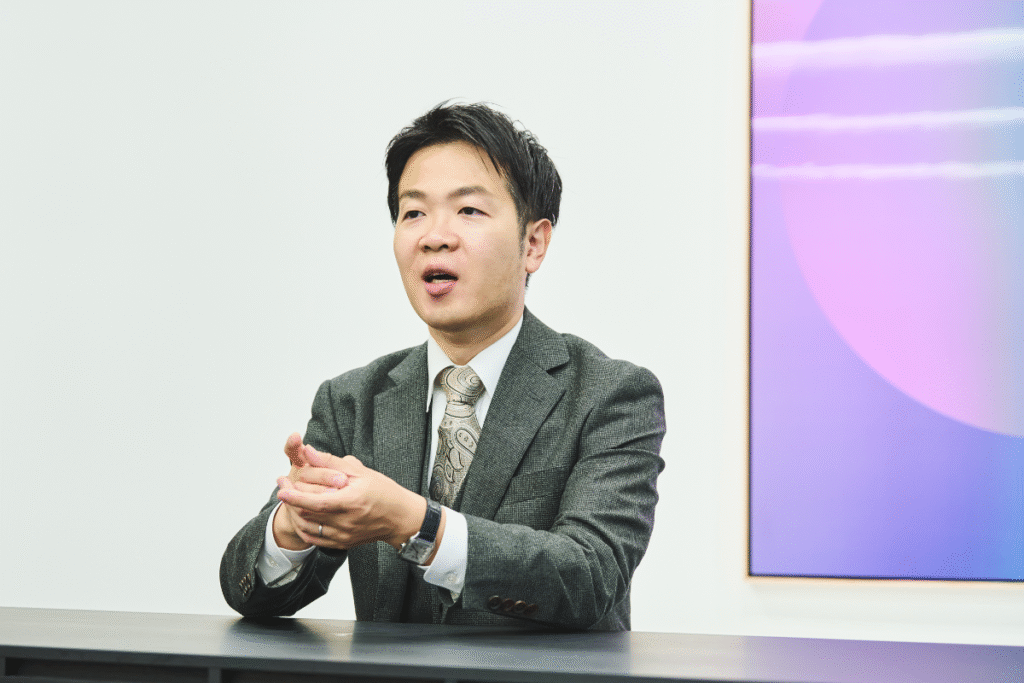
―ジュエリーに関心を持つようになったのは、どんなきっかけからだったのでしょう?
弁護士になって数年経ち、「自分の得意分野をつくりたい」と考え始めた頃に、たまたま損害保険の案件でジュエリーや時計に関する訴訟を担当したんです。評価や金額の妥当性が争点となり、職人さんや御徒町の問屋街に足を運んで話を聞いたりして勉強していたのですが、あるとき、「なぜこの価格になるのですか?」と尋ねたところ、「そんなの4Cの評価による。」と当然のように即答されて。
自分自身、業界の常識を全く理解できていなかったことに衝撃を受け、早速日本ジュエリー協会が出しているジュエリーコーディネーターのテキストを購入しました。ページをめくると、宝石の写真が数多く掲載されていて、すぐにその美しさに引き込まれました。子どもの頃に化石を集めたり、旅行先の鍾乳洞で石のサンプルを買ってもらったりした記憶が一気によみがえってきたんです。気づけば夢中になって読み込み、「せっかくだから資格を取ってみよう」と思うようになりました。
これまで他の案件で協会団体のテキストを調べることはあっても、資格まで挑戦しようと思ったことはなかったのですが、ジュエリーについては自然にその気持ちが湧いてきました。
―ジュエリーコーディネーターというのはどのような資格なのですか?
販売員さん向けの民間資格で、3級・2級・1級と段階があります。
3級は誕生石や基礎的な知識を学ぶ入門レベルで、新卒の方が店頭に立つ前に取得するようなイメージです。2級になると店舗運営や在庫管理などが問われ、店長クラスに必要な知識とされています。
そして1級はさらに高度で、マネージャーや経営者層を対象に、業界団体が「スペシャリスト」として推薦できる人物に与えられる資格です。試験も記述や論文に加え、ダイヤモンドのグレーディングや色石の評価、さらには接客ロールプレイングまで課される実技試験があります。単純な知識だけではなく、現場感覚を理解することが重視されている点が特徴です。
もちろん弁護士に必要な資格ではありません。ただ、現場で働く方々が持っている知識や感覚を知ることで、クライアントの方と共通言語で話せるようになる。そういった意味で、自分の仕事に大きくプラスになっていると感じています。
信頼と価値を守るため
知識を磨き業界に寄りそう
―新田先生にとってジュエリーの魅力とは?
ジュエリーの世界は、本当に奥深く、一言では語りきれません。
ダイヤモンドやエメラルドといった希少石や貴金属を用いたファインジュエリーの世界もあれば、素材そのものの価値にとらわれずデザインや発想で人を惹きつけるコスチュームジュエリーの分野もある。さらに古代ローマの指輪やヴィクトリア時代のブローチのように、アンティークを通じて歴史や文化に触れることもできる。近年では、アートやダンスと同じように自己表現の手段として生まれているコンテンポラリージュエリーも広がってきています。
独立した複数の世界が地図のように広がり、それぞれに奥行きがある。その全体像に触れるたびに、新しい学びと発見があることが、ジュエリーの最大の魅力だと感じています。
―小さな「ジュエリー」の中に、こんなに多様で奥深い世界が広がっているとは驚きました。
一方、実際の現場では美しい側面ばかりではありません。
小さくて高価なジュエリーは不正の対象になりやすい。実際には盗まれていないのに盗難を装ったり、損害額を水増ししたりと、さまざまな手口が存在します。そうしたときに、商流やリユース市場の動きを理解していると、不自然な点や矛盾を見抜けることがあります。逆に言えば、相談を受ける側に知識が不足していると、見逃されてしまうケースもある。だからこそ、業界の仕組みや慣行を学び続けることは欠かせませんし、その知識があるからこそ、業界の方々からの信頼にもつながっているのだと思います。
―ジュエリー業界では他にはどのようなトラブルやご相談が多いですか?
修理やリフォームのトラブルに関するご相談は多いですね。返却時に「こんな傷はなかった」「もっと鮮やかで大きな宝石だった」といった主観的な印象がトラブルにつながるケースです。
お客様から預かるジュエリーは、家族の思い出や人生の節目と深く結びついていることが多いため、とても繊細な問題になります。だからこそ、事前に写真を残す、注意事項を明確に伝えるといった仕組みづくりが欠かせないのです。
また、返品についてのご相談もよくあります。「婚約破棄になったから指輪を返品したい」など、法律的に見れば返品できないケースでも、高い顧客体験が求められるラグジュアリー産業では法的基準だけでは割りきれない部分があります。そうしたときに「どこまで寄り添うか」「どう対応すればブランドの価値や信頼を守れるか」をクライアントと一緒に考えるのも、私の役割の一つだと思っています。
BtoBの領域では、デザインの模倣や知的財産をめぐるトラブルが少なくありません。
ジュエリーは時代や流行を超えて長く販売されることが多いため、本来であれば意匠権の活用に適した分野です。ところが、ジュエリー業界は中小規模の事業者が多く、知財を専門に扱える人材や予算を確保するのが難しい。加えて、デザインと知財を結びつけて戦略的に捉える文化がまだ十分に根付いていない点も大きな課題です。こうした事情から、意匠権などの制度を十分に活用しきれず、制度が持つ「未然防止」や「ブランド強化」の側面を生かしきれていない企業が少なくないのが現状です。
だからこそ、今後は権利の守り方や活用の仕方を業界全体で意識していくことがますます重要になっていくと感じています。
―最後に今後の展望を教えてください。
歴史上の偉大なデザイナーや経営者の傍らには、華やかな表舞台からは見えませんが、彼らを支えた多くの存在があったと思います。例えばイヴ・サンローランを支えたピエール・ベルジェのように、優れた才能をそれに相応しいステージに連れて行くための手伝いをしたいと考えています。
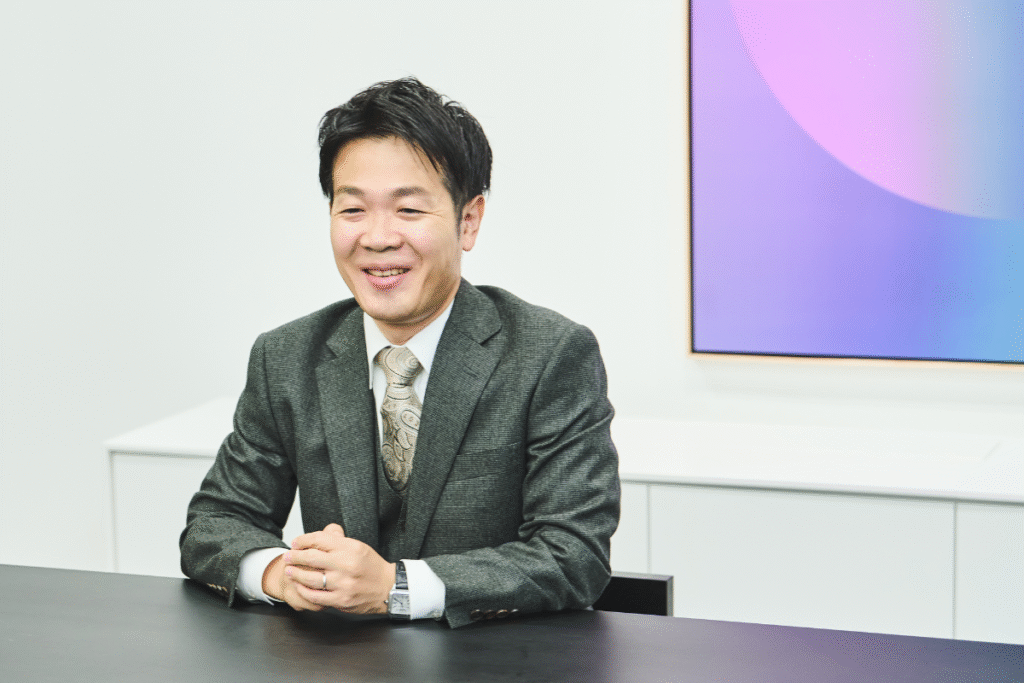
【2025.9.25】
三村小松法律事務所では、当事務所の理念や目標に共感し、チャレンジ精神をもって行動できる方、また各業界への関心やこれまでの経験を活かして成長したいと考える意欲ある弁護士を募集しています。
採用ページ
法律相談・メディア出演のご相談はこちら
お問い合わせMiKoTamaメルマガ
法律に関する様々な情報トピックをメルマガで配信