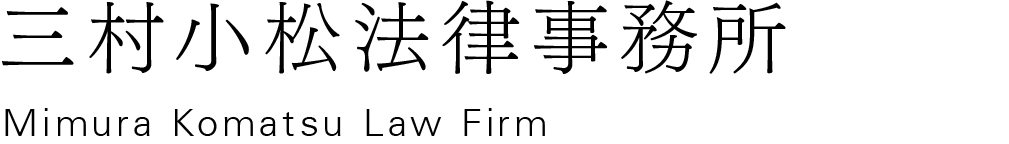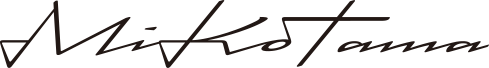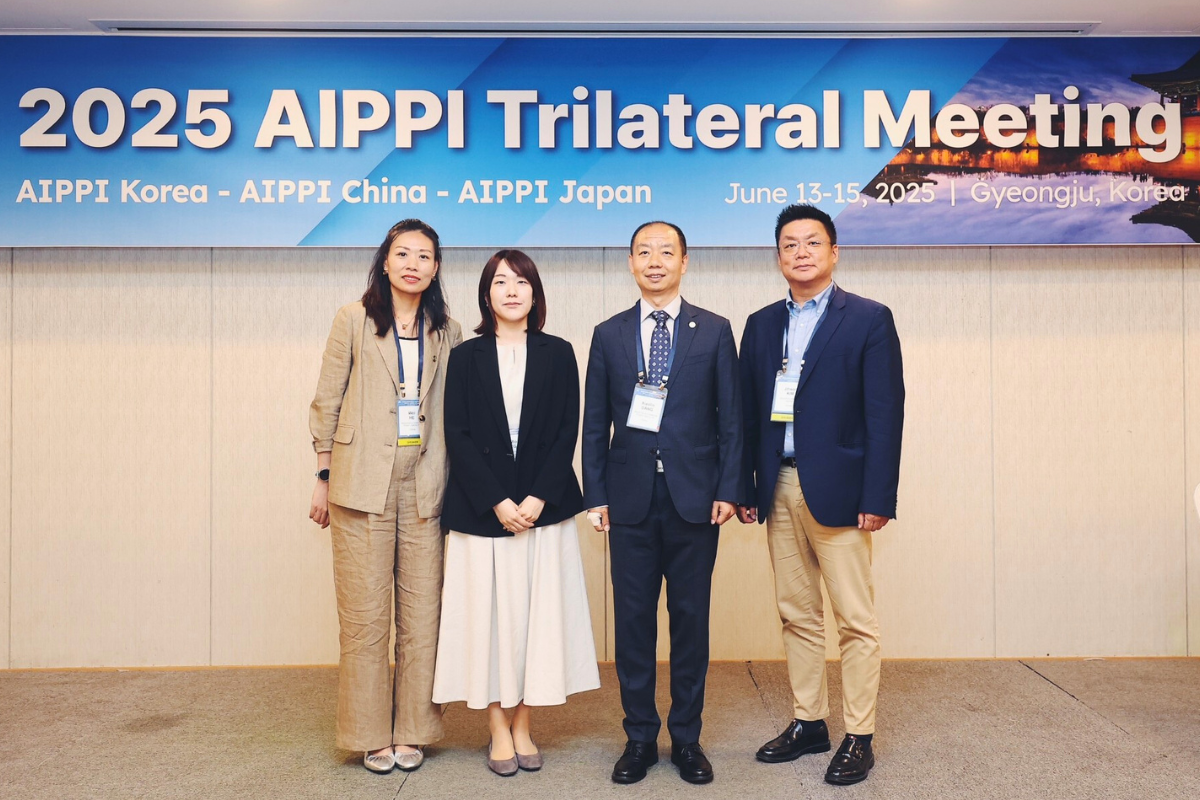ダンス講師やダンサーの方必見!
ダンス教室で音楽を利用する際の注意点
ようやく暑さがやわらぎ、秋の気配が近づく中、新しいスポーツなどに挑戦したいと感じている方も多いのではないでしょうか。かくいう筆者も、幼少期から学生時代まで習っていたクラシックバレエのレッスンを約10年ぶりに本格再開しました。
さて、バレエのレッスンに欠かせないのが音楽です。最近のバレエレッスンでは、おなじみのクラシック音楽だけでなく、ディズニーやジブリなど人気の音楽をレッスン用にアレンジした曲が使用されることも多く、音楽の幅がぐんと広がっています。
本記事では、バレエ教室で音楽を使う際に注意していただきたいポイントをQ&A形式でご紹介したいと思います。バレエだけでなく他のダンス教室にも共通する内容ですので、ぜひ講師やダンサーの皆さまにお読みいただけると嬉しいです。
【前提知識】
Q&Aに入る前に、音楽をめぐる著作権の基礎知識を整理しておきましょう。
著作権とは
音楽は、作曲家が曲を、作詞家が歌詞を創作しますよね。こうした曲や歌詞は、著作権によって保護されています。
- 著作権とは、創作物を創作した人(著作者)が、その創作物(著作物)を独占的に利用できる権利のこと。著作権で保護される著作物は、思想または感情を創作的に表現したもので、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものとされています。
- 著作権は、無断でコピーされない権利(複製権)、無断で著作物をインターネット配信などされない権利(公衆送信権)などの権利の総称です。音楽との関係では「演奏権」が特に重要ですが、これについてはQ&Aで詳しくご説明します。
- 著作権には、狭い意味での著作権とは別に、著作者人格権という権利があります。著作者人格権は、著作物の創作者として氏名をどのように表示するかを決められる氏名表示権や、著作物の表現などを改変されない同一性保持権などで構成されています。
- 著作権(狭い意味での著作権と著作者人格権)は、著作物を創作すると自動的に発生し、登録などが必要ないことも特徴の一つです。
さて、音楽には、作曲家、作詞家、アーティストなどさまざまな人が関わっていますよね。その人たちはどのような権利を持っているのでしょうか?
曲の創作者である作曲家、歌詞の創作者である作詞家は、基本的には著作権を持っています。作曲家や作詞家は、曲や歌詞が無断で使われた場合、その使用をやめるよう求めたり、損害賠償を請求することができるわけです。
アーティストや演奏者、レコード会社などは、曲や歌詞を創作したわけではないものの、音楽の伝達に重要な役割を果たしていますよね。そこで、これらの人たちにも、著作権法上、著作権とよく似た「著作隣接権」という権利が認められています。そのため、人気アイドルの曲をBGMにした動画をYouTubeに投稿する場合には、歌っているアイドルにも許諾を得なければならないわけです。
以上の知識を前提として、バレエ教室で音楽を利用する場合のポイントをQ&Aで見ていきましょう。
Q1 バレエ教室でのレッスンの際、ピアノで音楽を生演奏してもいい?
A1 作曲家の許諾を得よう。
バレエ教室では、講師がピアノを演奏し、それに合わせて生徒が練習することが少なくありません。
Q1を考える上でポイントになるのが、前提知識でも触れた「演奏権」です。演奏権とは、著作物を公衆に直接聞かせることを目的として演奏する権利のこと。
つまり、その曲を公衆に向けて演奏できるのは著作者である作曲家だけであり、それ以外の人が公衆で演奏するためには作曲家の許諾が必要ということになります(ただし、著作権法で定められている例外の場合は許諾は不要です。)。
ここで、「バレエ教室のレッスンで音楽を演奏することが、『公衆』に聞かせるための演奏に当たるの?」と疑問に思われた方も多いのではないでしょうか。
著作権法では、「公衆」とは、「不特定の者」または「特定多数の者」を意味するとされています。つまり、「特定かつ少数の者」は「公衆」に当たりません。
この「特定」かどうかは、演奏者と演奏を聞く人との間に個人的な結合関係があるかどうかにより判断するとされています。
参考になる裁判例をご紹介しましょう。
社交ダンス教室の授業で音楽を流すことが「公衆」に聞かせるためかどうかが争われた事案です。裁判所は、ダンス教室の受講生は、ある時点のある教室では特定かつ少数にとどまるものの、授業の受講資格が設けられておらず、希望すれば誰でも入会して受講できることや、授業によって受講生が入れ替わることから、教室と受講生の間に人的な結合関係はなく、「公衆」に聞かせるための演奏であると判断しました(名古屋地判平成15年2月7日)。
バレエ教室も、社交ダンス教室と同様、教室と生徒が受講契約を締結すれば誰でもレッスンを受けることができ、レッスンごとに生徒が入れ替わるのが一般的かと思います。そうすると、バレエレッスンで音楽を演奏することも、「公衆」に聞かせるための演奏に当たると考えられます。
バレエ教室のレッスンで音楽を演奏する場合は、忘れずに作曲家の許諾を得るようにしましょう。
クラシック音楽を利用する場合は、Q6をご覧ください。 また、作曲家を含む著作者から許諾を得る方法については、Q7を参考にしてください。
Q2 では、プレイヤーでCDを流すだけならOK?
A2 CDの音源を流す場合も、権利者の許諾が必要!
Q1で説明した「演奏権」には、著作権法上、演奏の録音物や録画物を再生することも含むとされています。そのため、レッスンでCDの音源を流すことも、ピアノを演奏する場合と同様に、「公衆」に聞かせるために演奏する場合に当たります。
したがって、CDの音源を流す場合にも、権利者の許諾を得る必要があります。
なお、アーティストが歌っている曲のCDであれば歌詞が入っていますので、作詞家の許諾も必要になります。
では、歌を歌っているアーティストや演奏しているバンド・オーケストラ、レコード会社などの許諾も必要かというと、実は必要ありません。
前提知識でご説明したとおり、アーティストや演奏者、レコード会社などは、著作権によく似た著作隣接権を持つのですが、この著作隣接権には上演・演奏権が含まれていません。そのため、CDを流す際にアーティスの歌声やバンドの演奏が流れても、アーティストや演奏者、レコード会社などはこれに対して何も言えないのです。
Q3 自分のデバイスを使ってApple MusicやSpotifyから音楽を流してもいい?
A3 利用規約に違反する可能性が!
Apple MusicやSpotifyなどの音楽配信サービスは、利用規約で「私的な利用」のみを認めているのが一般的です。
バレエ教室で、生徒から金銭を受領した上でレッスンのために音楽を流すことは商用利用にあたり、「私的な利用」には当たりません。そのため、バレエ教室のレッスンでApple MusicやSpotifyなどの音楽配信サービスの音源を流すことは、各サービスの利用規約に違反する可能性があります。
利用規約に違反する場合は、Q2と同じく許諾が必要となりますので注意が必要です。
音楽配信サービスの音源を使用したい場合は、利用規約を十分確認するようにしていただければと思います。
Q4 オンラインレッスンを行う場合も許諾が必要?
A4 ネットで配信する権利についても許諾を得ることが必要!
オンラインレッスンの方法はいくつかあると思いますが、ここでは、スタジオでCDの音源を流してレッスンを行い、同時にその映像をオンラインで配信する方法を例としてご説明します。
スタジオでCDの音源を流すことについては、Q2と同じく著作権者に演奏権についての許諾を得る必要があります。加えて、オンラインレッスンの場合は音楽をインターネットで配信することになりますので、インターネット配信などされない権利(公衆送信権)の許諾も必要ということになります。
では、Q2と同じく歌を歌っているアーティストや演奏しているバンド・オーケストラなどの実演家、レコード会社などの許諾は必要ないのでしょうか?
実は、著作隣接権には「送信可能化権」が含まれていることから、実演家やレコード会社もインターネット等で配信する権利を専有しています。そのため、CDの音源を使用してオンラインレッスンを行う場合は、実演家やレコード会社からも許諾を得る必要があります。
実演家の多くは、レコード会社との契約で、レコード会社に対して著作隣接権を譲渡していることが多いと思われます。そのため、実演家に許諾を取る際は、まずはレコード会社にコンタクトするのがよいでしょう。
Q5 レッスン風景の動画をSNSに投稿したい! どこに気を付ければいい?
A5 録音・録画する権利とインターネットで配信する権利について許諾を得ることが必要!
前提知識で少し触れましたが、著作者である作曲家には、制作した音楽を無断でコピーされない権利(複製権)が認められています。
レッスン風景を動画に撮影する場合、レッスン中に流れている音楽を録音する、つまりコピーすることになりますので、複製権について許諾を得る必要があります。
また、撮影した動画を、音楽を消さないままSNSに投稿することは、オンラインレッスンと同様に音楽をインターネットで配信することになりますのでQ4と同じく、インターネットで配信などされない権利(公衆送信権)の許諾も必要ということになります。
実演家やレコード会社に対してはどうでしょうか?
実演家やレコード会社に認められている著作隣接権に送信可能化権が含まれていることはQ4でご説明しましたが、著作隣接権には、音楽をコピーされない権利(複製権)も含まれています。
つまり、レッスン風景の動画をSNSに投稿する場合には、実演家やレコード会社からも、送信可能化権と複製権の許諾を得る必要があるということになります。
Q6 クラシック音楽なら著作権が切れているから大丈夫だよね?
A6 原則として、著作者の死後70年が経過している音楽は使用可能と考えられるものの、十分チェックが必要!
著作権の保護期間は、原則として、著作者の死後70年を経過するまでの間とされています(例外もあります。)。そのため、著作者の死後70年が経過している音楽は、自由に使用することができることになります。例えば、「くるみ割り人形」は作曲家のチャイコフスキーが1893年に亡くなっており、死後70年を経過しているため、著作権の許諾を得ずに演奏することができます。
もっとも、著作権の保護期間が切れているかどうかは、戦時加算など複雑な制度もあり、判断が難しいのが実情です。
また、使いたい曲が、実は原曲をアレンジした曲だった場合、アレンジした部分には編曲者に著作権が発生しますので、編曲者の許諾を得る必要があります。 古い作品でも、安易に著作権が切れていると判断せず、十分確認するようにしてください。
Q7 音楽の許諾はどうやってとったらいい?
A7 著作者である作詞家や作曲家の多くは、著作権の管理をJASRACやNextone等の著作権等管理事業者に委託していることが多いため、実際はJASRAC等に許諾を得る必要があることが多いです。
そのため、まずは、演奏したい音楽がJASRAC等に管理されている音楽であるのかをJASRAC等のデータベースで調査し、JASRAC等が管理していると判明した場合は、JASRAC等の指定する方法で許諾申請をし、使用料を支払うことになります。
ダンスと音楽は切っても切れない関係にあります。好きな音楽に合わせて体を動かす爽快感は多くの人が味わったことがあるのではないでしょうか。
だからこそ、音楽を利用するときにはルールをきちんと守ることが大切です。 正しい理解と準備があれば、安心してレッスンを楽しむことができます。本記事が、その第一歩となれば幸いです。
音楽著作権についてお悩みの方は是非 三村小松法律事務所 へご相談ください。
【2025.9.12】
法律相談・メディア出演のご相談はこちら
お問い合わせMiKoTamaメルマガ
法律に関する様々な情報トピックをメルマガで配信