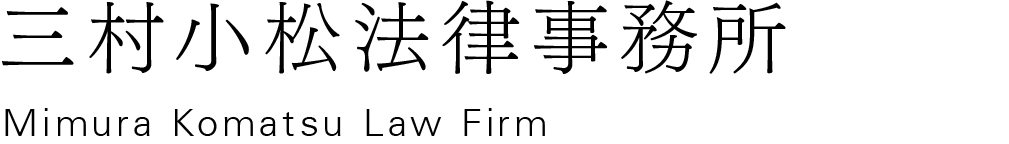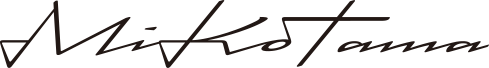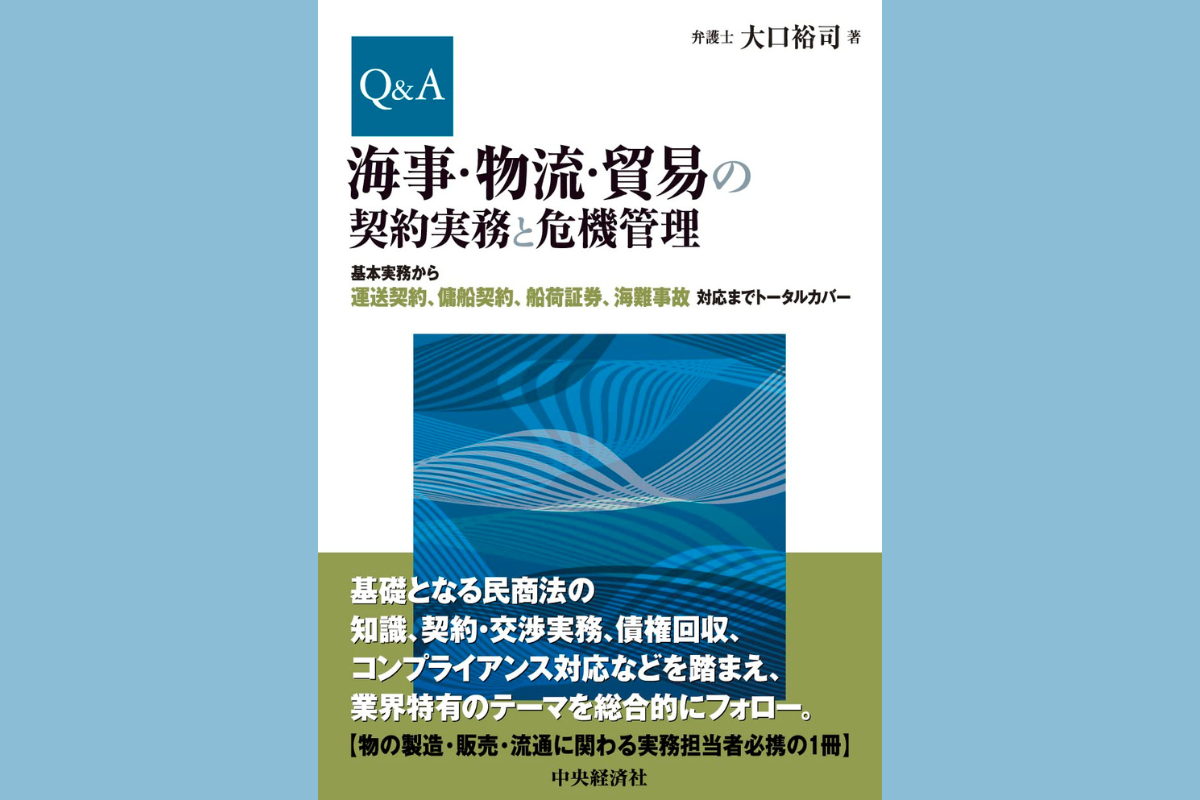
【海事・物流部門】
海事・物流・貿易における債権回収と保全 ~これら分野を得意とする弁護士によるポイント解説~
物流は企業にとって重要な関心事でありながら、社会的・経済的な問題の影響を受けやすく、実務上、さまざまなトラブルが生じます。
当事務所の海事・物流部門代表である大口裕司弁護士は、最近の相談事例として、ロシア・ウクライナ間の武力紛争に起因する物流トラブルを挙げています。
たとえば、日本法人がウクライナ法人に物品を売却し、海上輸送中にウクライナ法人が貨物の受取りを拒否し、運送が断念されたというケース。このとき、運賃が後払いであった場合に「荷受人であるウクライナ法人から支払いが見込めない場合、誰が運賃を負担するのか」という点が問題となります。
大口弁護士は「運送契約の基本は荷送人・運送人間の契約なので、運送人は荷送人(日本法人)からの回収を考えることになります。これは商法581条3項にも沿う考え方といえます。」と説明します。
このように、物流に関する紛争やトラブルが生じた際に的確な対応を取るためには、運送契約や関係法令に対する基本的な理解が欠かせません。
そうした基礎的な法理解を広く学ぶことができるのが、大口弁護士が執筆した『Q&A 海事・物流・貿易の契約実務と危機管理―基本実務から運送契約、傭船契約、船荷証券、海難事故対応までトータルカバー』(中央経済社)です。
今回はその中から、「債権の回収と保全」のポイントについて解説していただきました。
債権回収の検討事項・順序
債権回収の際には、以下のように考えていきます。
⑴ 準拠法(や裁判管轄)
どこの国の法律が適用されるかによって解釈が変わってくるので、まずは準拠法(や裁判管轄)の規定を確認しましょう。著者の経験上、この点の確認をせずに日本法が適用されると思い込んでいる企業の方も多いです。
海外法が準拠法となる場合は海外弁護士のアポイントを検討しますが、物流を得意とする弁護士は、通常、様々な国の海外弁護士とのコネクションを持っていますので、安心してください。
⑵ 請求根拠・原因、権利者、義務者
次に、契約に基づく責任を問うのか、契約に基づかない責任(不法行為など)を問うのかを区分したうえで、誰が誰に対して、どのような根拠・原因で請求するのか、それに関連した証拠や反論はどのようなものがあるのかを検討してください。
例えば、貨物損害の契約責任を追及する場合、船荷証券が発行されているなら、通常、権利者は船荷証券の正当所持人、義務者は船荷証券の運送人署名欄に運送人として記載されている者と考えておけばよいです。
⑶ 和解の検討
上記⑵を検討したうえで、訴訟になった場合にどの程度勝てそうかの予想をしてください。もっとも、弁護士でないとそのあたりの予想は難しいかもしれません。
この予想を踏まえて和解の可能性と水準を検討し、話合いによる解決を模索します。法的手段で解決しようとすると、弁護士費用等のコストが跳ね上がりますから、合理的な水準で話合いによる解決ができるならその方がよいと思います。
債権回収の手段
債権回収の手段としては、交渉、担保権の行使や相殺、訴訟や仲裁があります。
⑴ 交渉による回収
一口に交渉による回収と言っても、いろいろな方法があり、状況に応じて使い分ける必要があります。
例えば対面交渉は、相手の表情や声色などから得られる情報もあって有益かもしれませんが、口頭での交渉なので、言ったことを後で覆される可能性もあります。メールで交渉する場合には、そういったリスクが軽減できますが、文章にするので慎重になりすぎて交渉が前進しにくいこともあります。
弁護士を介して交渉するのがよいかどうかも、ケースバイケースです。弁護士名義の内容証明郵便を送ることで即座に解決することもあれば、逆に、それをきっかけに相手方の態度が硬化することもありえます。
⑵ 担保権の行使や相殺
相手方に対して債務を負っていれば、自分が持っている債権と相殺することで、債権回収したのと同様の状態を作り出すことができます。債務をうまく活用する視点を持ってもらえればと思います。
担保権については、当事者間の合意で設定することもできますが、海事・物流・貿易の世界では、後で述べるような法律の規定に基づいて発生する担保権もあります。
⑶ 訴訟や仲裁
交渉による解決が困難であれば、訴訟や仲裁で回収することを考えますが、勝訴しても相手方にめぼしい財産がなければ「絵に描いた餅」です。それゆえ、訴訟や仲裁を始める前に、相手方の財産を仮差押えすることも検討すべきです。場合によっては、仮差押え自体が相手方へのプレッシャーとなって、それを契機に早期和解に至ることもあります。
海事・物流・貿易の世界の担保権
以下では日本法のもとでの説明をしていますが、海外法が適用されることもあるので、最初に準拠法を検討するのをお忘れなく。
⑴ 船会社が相手方の場合
船会社から回収する場合、船舶に対する権利行使が効果的です。船は莫大なお金をかけて建造され、船会社はそれを運航することで相当な収入を得ますが、船舶への権利行使によって運航が止まれば大きな損失となるので、船会社としては避けたい事態です。実際に権利行使しなくても、権利行使を予告しただけで和解に至るケースもあります。
例えば荷主が海難事故によって貨物に関する損害を被ったときは、船舶先取特権という担保権を利用した債権回収を検討することになります。荷主以外だと、例えば船舶に燃料や備品等を供給した企業や、船舶を検査・修繕した企業も、船舶に対する先取特権を行使できることがあります。
⑵ 貨物関係者が相手方の場合
貨物関係者から回収する場合、貨物に対する権利行使が効果的です。運送人なら、貨物の留置権という担保権の行使を検討しましょう。もっとも、留置権行使にあたっては、保管の場所や費用を考慮に入れる必要があるので、注意が必要です。
貨物の売買当事者間で代金未払いがある場合には、売主はその物に対して先取特権を行使することで回収を図ることが考えられます。但し、買主が転売・引渡しする前に行使する必要があるので、注意が必要です。
債権保全のために平常時にすべきこと
債権回収の問題が起きないように、あるいは起きても解決しやすいように、平常時のポイントを挙げます。
⑴ 相手方との契約時までにすべきこと
債権保全の観点から、契約書のドラフトは極めて重要ですが、リーガルチェックを入れていない企業も多い印象です。できるだけ貴社にとって有利な条項にしておけば、何か問題が起きたとしても、相手方は反論しても認められる可能性が低いと考え、和解での解決に応じやすいこともあります。
また、契約交渉の段階から、相手方とのやり取りは保存しておくべきです。口頭でのやり取りも、議事録等の形で文書化して保存することをお勧めします。取引開始後、何年も経ってから取引上の解釈疑義が生じ、当初の企業担当者はどのように考えていたのかが問題となるケースがあります。その担当者が退職していて話が聞けないこともありますが、在籍していても、何年も前のことで覚えていないことも多いです。
⑵ 相手方と契約した後にすべきこと
(債権回収含め)トラブル解決の一つのポイントは、できるだけ速やかに動くことです。対応が遅れ、相手方が倒産危機に陥った場合、倒産法によって債権回収が制限されることもあります。
その点からして、契約締結後も、相手方とはコミュニケーションを続け、時々は会社訪問して情報取得するのがよいです。会社を訪問することで見えてくることもあると思います。時には一緒に飲食し、仲良くなることで得られるものもあると思います。
企業を作っているのは人ですから、トラブルが生じても、「〇〇さんがそう言うなら・・・」ということで解決することもあります。良好な人間関係があれば、法を超えた解決もしやすくなります。
債権回収・保全における重要なポイント
海事・物流・貿易の分野は、
- 専門性が高い
- 国際取引の知識と英語力が必須
- 様々な国の海外弁護士とのコネクションが必要
- 特殊な法律や条約が多い
- 実務と法が密接に関連しているので、実務を知る必要がある
などの理由により、一般の弁護士があまり扱わない特殊な分野です。そのため、企業にとって一番のポイントは、この分野を得意とする弁護士とのコネクションを持っておき、いつでも気軽に相談できる体制にあるかどうかだと思います。いざトラブルが起きたときに探そうとしても、すぐには見つからないかもしれませんし、見つかったとしも、電話相談は受け付けていないと言われたり、かといって面談の予約を取ろうとしても、弁護士が多忙で予約が入りづらかったりすることもあると思います。そうならないように、事前に顧問契約を締結しておくのがベストですが、少なくとも、平常時から関係性を築いておくのがよいと思います。
なお、複数の法律事務所とコネクションを持っておき、案件によって使い分けるのも一案です。
【2025.7.22】
法律相談・メディア出演のご相談はこちら
お問い合わせMiKoTamaメルマガ
法律に関する様々な情報トピックをメルマガで配信